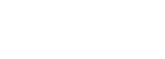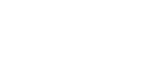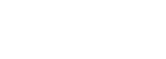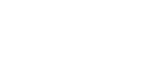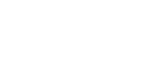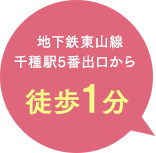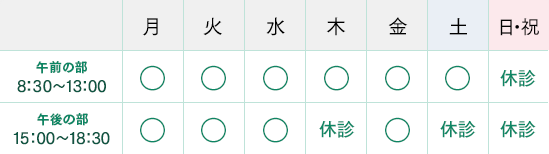糖尿病と心房細動(その1)
Ⅰ はじめに
心房細動は今日、最も多くみられる不整脈の1つになりました。心房細動を定義すると、「心房が洞結節の刺激のよらずに速く部分的に興奮収縮して、規則的な洞房結節の活動が伝わらないために、心室の収縮が不規則な間隔で起こる状態」となります。このような定義をみる、心房細動が無機質で孤発的な現象に過ぎない印象を与えますが、この不整脈は驚くほど多彩な疾患と有機的にリンクしています。心房細動は心不全、呼吸器疾患、癌などのあらゆる疾患の終末像として出現し得ます。一般的には、心房細動は加齢と共に増加します。心房細動はまた、心房収縮不全による心拍出量低下と頻脈によって心不全を引き起こしうるほか、左房内血栓による脳梗塞が重大な合併症として知られています。心房細動の病態の核となるのは左房にリモデリング(心臓が血行力学的負荷に対して循環動態を一定に保つために構造と形態を変化させること)ですが、さまざまな原因による左房へのストレッチ刺激とともに、全身のサイトカインや炎症の活動亢進が左房にも及んで左房リモデリングを進行させることが明らかとなったため、心房細動の病態の本質部分が「生活習慣病」による全身の動脈硬化促進と類似していて、互いにリンクしていることが今日では広く認識されてきています。
その意味では、糖尿病は心房細動への発症自体に深く関与しうる病態です。糖尿病を長期罹患しているためにおこる糖化反応(グリケーション)により網膜症、腎症、神経障害といった三大合併症が生じるほか、種々の疾患リスクを高めることが知られています。
Ⅱ 心房細動発症に対する糖尿病の関わり
糖尿病患者では心房細動のリスクが高いことが知られていますが、この原因の筆頭にあげられるのは、糖尿病そのものよりもまずその多彩な合併症であると考えられます。糖尿病患者は高血圧、冠動脈疾患、心不全、心肥大を伴いやすく、これらが心房細動を引き起こしているという考えです。一方で、高血糖が持続することで引き起こされる糖化反応により生じた終末糖化産物が血管内皮細胞増殖因子の産生亢進を促して動脈硬化を促進します。これが左房のリモデリングを促進して、心房内伝導障害を来すことが知られています。このような直接・間接的な病態で糖尿病と心房細動が結びついているのです。
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月