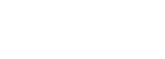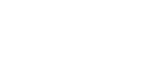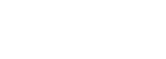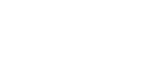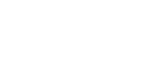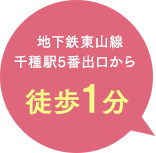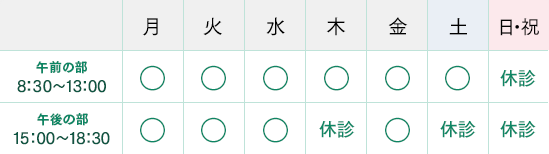亜鉛欠乏症について(その1)
Ⅰ はじめに
1961年にヒトでの亜鉛欠乏症が最初に報告されました。今日でも亜鉛欠乏症は発展途上国を中心として世界で20億人が罹患しています。我が国の亜鉛欠乏症の発症率は15~25%と先進国の中では最も高いと報告されています。また、亜鉛欠乏症の症状は非常に多彩で、亜鉛欠乏症に気がついていない患者さんも多くみられます。一方、2017年3月に低亜鉛血症に対して酢酸亜鉛製剤が我が国で初めて使用可能になりました。
Ⅱ 亜鉛の吸収・体内動態・排泄
食事中の亜鉛は主に十二指腸、空腸で吸収されますが、その吸収率は約30%です。腸管から吸収された亜鉛は、血中でアルブミンまたはα2マクログロブリンと結合して全身に運ばれます。血液中の亜鉛の約80%が赤血球、約20%が血清、約3%が血小板や白血球に存在します。
亜鉛の細胞内恒常性の維持には亜鉛トランスポーターが働いていますが、腸管での亜鉛吸収を司る遺伝子に異常があると先天性腸性肢端皮膚炎になります。乳腺細胞から乳汁への亜鉛分泌を司る遺伝子異常がある母親の乳汁中に含まれる亜鉛濃度は著明に低く、その母乳のみを授乳している乳児は一過性亜鉛欠乏症を発症します。我が国では20例以上の報告があります。
亜鉛の主な排泄経路は膵液から腸管への排泄です。尿中への排泄は極めて少なく、汗からも排泄されます。亜鉛は生体内に広く分布していて、筋肉(60%)、骨(20~30%)、皮膚・毛髪(8%)、肝臓(4~6%)、消化管・膵臓(2.8%)、脾臓(1.6%)、その他腎臓、脳、血液、前立腺や眼などの臓器にも多く存在します。
Ⅲ 亜鉛の摂取推奨量と摂取量
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、亜鉛摂取の推奨量は、成人男性で11mg/日、女性で8mg/日ですが、妊婦では2mg/日、授乳婦では3mg/日を付加することになっています。一方、厚生労働省が発表した2019年の国民健康・栄養調査報告によると、20代以降の平均亜鉛摂取量は男女共に推奨量より少なく、摂取不足気味といえます。特に、妊婦・授乳婦の摂取量は推奨量に比べて著しく少ないことが報告されています。
Ⅳ 亜鉛の体内での働き
亜鉛は300種類以上の酵素の活性化に必要な成分で、細胞分裂や核酸代謝などにも重要な役割を果たします。そのため酵素活性に働く亜鉛の生理作用は多彩で、①身長の伸び(小児)、②皮膚代謝、③生殖機能(特に男性)、④骨格の発育、⑤味覚の維持、⑥精神・行動への影響、⑦免疫機能などに関与しています。
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月