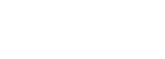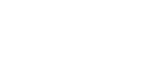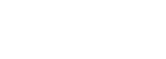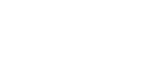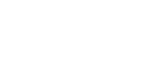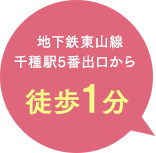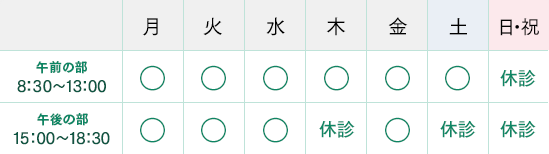亜鉛欠乏症について(その2)
Ⅵ 亜鉛欠乏の要因と症状・病態
亜鉛欠乏来す要因としては、
摂取不足:低亜鉛母乳栄養(乳児期早期に発症)、低亜鉛食(動物性タンパクの少ない食事:菜食主義者)、静脈栄養で亜鉛補給が不十分、低栄養、高齢者
吸収不全:先天性腸性肢端皮膚炎(乳児期早期に発症)、慢性肝障害(慢性肝炎、肝硬 変)、炎症性腸疾患、フィチン酸・食物繊維の過剰摂取(亜鉛吸収を阻害する)
需要増大:低出生体重児で母乳栄養(乳児期の体重増加が著しい時期に発症)、妊婦
排泄増大:キレート作用のある薬剤の長期服用、糖尿病、腎疾患、溶血性貧血、血液透析
その他:スポーツ
などがあります。亜鉛が欠乏すると亜鉛酵素の活性が低下して、その結果、障害・症状が発症します。亜鉛欠乏による障害・症状は、タンパク合成が盛んな細胞や臓器、また亜鉛が高濃度に存在する細胞や臓器でも生じやすいことが知られています。
皮膚炎:特徴として、開口部(口、鼻、臀部など)や爪の周囲に発症します。また、機械的刺激 のある皮膚(乳幼児の後頭部など)にも発症しやすいとされています。
味覚障害:亜鉛欠乏の特徴的な症状です。
貧血:赤芽球の分化・増殖が障害されて貧血を起こします。スポーツ選手では、亜鉛欠乏により赤血球膜の抵抗性が減弱するため、強度の機械的刺激などにより溶血して貧血になります。
易感染性:亜鉛欠乏で感染症に関与する白血球の貪食能低下、ナチュラルキラー細胞の減少、胸腺の萎縮などが起きます。また、亜鉛欠乏では感染症に罹患しやすくなり、重
症化しやすくなります。
性腺機能不全:精巣には高濃度の亜鉛が存在します。亜鉛欠乏で、性欲の減退や精子数の減少が起こり、男性不妊の原因となります。
発育不全:体重増加不良や低身長になります。
Ⅶ 亜鉛欠乏症の診断と治療
1 診断:早朝空腹時で採血した血清で診断
60μg/dL以下 亜鉛欠乏症
60~80μg/dL未満 潜在性亜鉛欠乏
2 食事療法:牡蠣、肉類のレバー、牛肉、ウナギ、米、豆腐などの亜鉛含有量の多い食品を積極的に摂るようにします。
3 治療:硝酸亜鉛を学童以降から成人では50~150mg/日、幼児では25~50mg/日、乳幼児・小児では1~3mg/Kg/日を目安に内服します。
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月