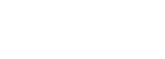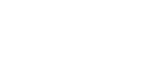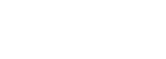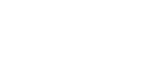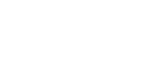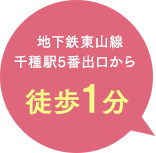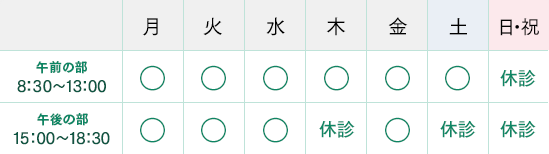動脈硬化予防のための運動療法(その1)
Ⅰ はじめに
2型糖尿病患者で、有酸素運動やレジスタンス運動、あるいはその組み合わせによる運動療法は、血糖コントロールや心血管疾患のリスクファクターを改善します。2型糖尿病患者に対する有酸素運動とレジスタンス運動は、ともに単独で血糖コントロールに有効で、併用することによりさらに効果が高まります。
Ⅱ 運動療法の効果
2型糖尿病患者に対する運動療法は、血糖コントロールを改善して、心血管疾患のリスクファクターである肥満、内臓脂肪の蓄積、インスリン抵抗性、脂質異常症、高血圧、慢性炎症を改善します。血糖改善効果は、その介入期間や強度、頻度、運動の種類により異なりますが、8週間以上の運動療法に関するメタ解析(平均3.4回/週、18週間)では、有意な体重減少は認められませんでしたが、HbA1cは有意に改善した(ー0.66%)したと報告されています。
また、運動療法による2型糖尿病患者の心肺機能に及ぼす影響についてのメタ解析では、平均して最大酸素摂取量の50~75%の強度の運動を1回約50分間、20週間行った場合、最大酸素摂取量は有意に増加(11.8%)したと報告されました。
近年では、高強度インターバルトレーニングの有用性が示されつつあります。高強度インターバルトレーニングの効果を検討したメタ解析では、メタボリックシンドロームや2型糖尿病に対する2~16週間の介入で、対照群に比べて、空腹時血糖値やHbA1cの改善効果を認めましたが。持続的な運動を行った群との比較では有意な改善効果は認められませんでした。短時間の高強度運動のより長期的な血糖コントロール改善効果や安全性については不明です。
これらのエビデンスにより、現在のところ、週に150分以上、(3日以上にわたり、活動がない日が連続して2日を超えないように)の中等度~強度の有酸素運動を行うことが勧められています。また、若年者や心肺機能が高い患者は、高強度またはインターバルトレーニング運動であれば、より少ない時間(75分/週)でも同じ効果が得られると考えられています。
近年、レジスタンス運動のエビデンスが蓄積されてきています。レジスタンス運動では、筋肉量や筋力を増加させると共にインスリン抵抗性を改善し、血糖コントロールを改善します。一般的には週に2~3日、主要な筋肉群を含んだ8~10種類のレジスタンス運動を10~15回繰り返す(1セット)より開始し、徐々に強度やセット数を増加させることが推奨されています。有酸素運動単独、レジスタンス運動単独と、それらの組み合わせを比較した検討では、両者を組み合わせることでHbA1c低下効果が高まることが示されています。また、レジスタンス運動のHb A1c低下効果が、有酸素運動に劣らないことも示されていて、高齢者などで有酸素運動が困難な患者での選択肢となる可能性があります。実際に、高齢者でも有効性を示すエビデンスがあり、今後のより積極的な導入が期待されています。
また、運動のみならず、日常生活において生活活動を増加させることも体重の減少や予後改善に促進的に働くことが示唆されています。日常生活活動によるエネルギー消費は、肥満者と標準体重の者では大きな差があり、それが肥満の形成に大きく影響することが示唆されているほか、日常生活で座位の時間が長いほど死亡率と心血管疾患が増加することも示されています。2型糖尿病患者においては、30分に一度軽い運動を行うと、座位を維持したときよりも食後血糖が改善することが示されていて、座位時間が30分を超えたら一度座位を打ち切り、軽い運動を行うことが勧められます。さらに、疫学的に糖尿病患者で運動と生活活動を併せた身体活動が高い人ほど心血管疾患の発症や総死亡率が低いことが示されています。
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月