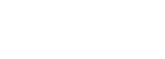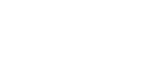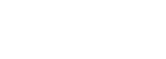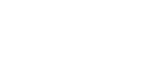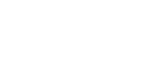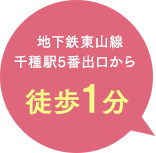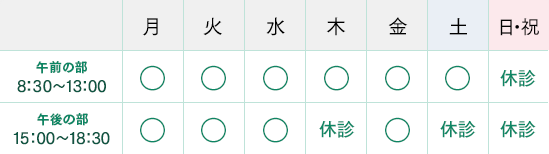睡眠障害の重要性(その2)
Ⅲ 睡眠障害の種類とその特徴
1)不眠症
我が国では、5人に1人が何らかの不眠を有するといわれています。不眠とは、睡眠に関する自覚的な訴えであり、「睡眠障害国際分類第3版」(米国睡眠医学会2018年)では、睡眠の機会が十分であるのにもかかわらず、入眠障害、頻回の覚醒ならびに早朝覚醒のいずれかかあり、1週間に3回、少なくとも3ヶ月以上続く場合とされています。また、ここでいう不眠は、客観的な睡眠障害が明らかでなく、睡眠不足に相応する日中障害がなく、これらに加え、他の睡眠覚醒障害、すなわち原発性睡眠障害では説明されないものと厳密には定義されています。
不眠症は、眠れないことによる日中の眠気や倦怠感、生産効率の低下、ひいては交通事故を引き起こす場合もあるばかりでなく、抑うつ症状や身体への影響として生活習慣病とも関連するため、適切な治療を受けることが望まれます。
(1)不眠と関連する身体疾患と薬剤
うつ病、心疾患、疼痛性疾患ならびに認知症では、多くの慢性疾患の合併は不眠の原因となります。また、かゆみ、咳ならびに頻尿などの症状の他、ニコチンやカフェインの摂取も不眠を起こす原因となります。就寝前のアルコールは、一見睡眠導入によいようにみえますが、睡眠の質を下げ、不眠の原因となる他、睡眠時無呼吸を悪化させます。薬剤でも、三環系抗うつ薬や気管支拡張薬、中枢神経刺激薬、SSRIなども不眠を引き起こす原因となります。
(2)不眠の影響
不眠は、抑うつや不安、生活に質の低下を引き起こし、その状態が続くと、身体・精神活動へ悪影響を及ぼします。総睡眠時間の減少、睡眠効率の低下や中途覚醒の増加ならびに浅く分断された睡眠は、高齢者では歩行スピードの低下、椅子からの立ち上がりや狭い歩幅の歩行等のパフォーマンスに悪い影響を与えます。重要な影響として、不眠は注意力、反応時間の遅延、ひいては記憶障害といった認知機能の低下との関わりがみられます。睡眠時間の減少は睡眠導入薬の影響を差し引いても、転倒リスクと関連すると報告されています。
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月