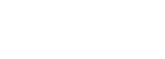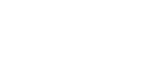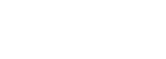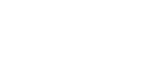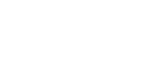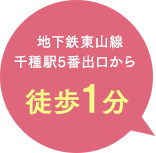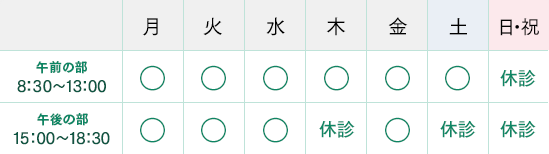糖尿病と心不全について(その2)
Ⅲ 糖尿病と心不全の関連に関するメカニズム
1)糖尿病の存在による心不全の増悪
糖尿病患者では、高率で虚血性心疾患を合併していることが多くあります。糖尿病による神経障害で必ずしも典型的な胸部圧迫症状を自覚しないこともあるため症状の有無で判断することはできません。糖尿病があると、冠動脈の慢性炎症や動脈硬化が進行して血管平滑筋の増殖や内皮障害が増悪することで虚血性心疾患が進行していきます。この虚血性心疾患が進行することで心機能が徐々に低下していきます。
糖尿病があると虚血性心疾患を通してだけでなく直接的な心筋障害によっても心機能障害をもたらします。これを糖尿病性心筋症といいます。インスリン抵抗性や高インスリン血症、糖尿病性自律神経障害によって心筋の線維化、慢性炎症、微小循環障害が進行して心筋の拡張障害や収縮障害が生じます。
2)心不全による糖尿病の増悪
心不全による神経体液性因子の不必要な活性化、特にレニン・アンジオテンシン系の賦活化によって脂肪酸代謝に影響を与えることで、インスリン抵抗性の増大や糖尿病の悪化に繋がるとされています。増悪した糖尿病が心不全を悪化させるという悪循環に陥るのです。
Ⅳ 糖尿病に合併した心不全に対する治療
1)薬物療法
心不全は進行性の病態のため、無症状のものでも心不全の危険因子を持っている段階から早期介入を行う必要があり、主に薬物療法を行います。この薬物療法は心不全治療の根幹をなすもので、どの段階でも継続する必要があります。
収縮能が低下したもののみを心不全と呼んでいた歴史的な経緯があるために、多くの薬物治療のエビデンスは収縮能が低下した心不全治療で確立されてきました。その中でもβ遮断薬は新機能の改善や予後改善効果のために最も重要な薬物治療の1つです。
心不全の主体は不必要に賦活化されたレニン・アンジオテンシン系による悪影響であるとの考えの下、この系を抑制するACE阻害薬やアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬も心不全治療薬として必要不可欠といえます。
上記薬剤を用いても改善しない重症心不全にはミネラルコルチコイド受容体拮抗薬を併用します。うっ血による症状を緩和する目的で利尿薬は必要不可欠ですが、高用量の利尿剤は心不全を悪化させるとされています。
近年、糖尿病治療薬のSGLT2阻害薬が心不全の再燃を予防できる可能性が示され、さらに一次予防にも有効とする成績も得られています。
2)非薬物療法
薬物療法で改善しないうっ血を伴う心不全患者に対しては、陽圧換気を用いた非侵襲性陽圧換気療法が行われます。電気的に心臓の収縮を再同期させる心臓再同期療法や、末梢血管を温熱の力で緩徐に拡張させることで心負荷を軽減させる和温療法なども行われています。何れの治療も糖尿病の有無による有効性の違いは明らかではありません。
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月