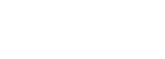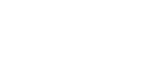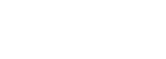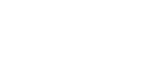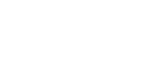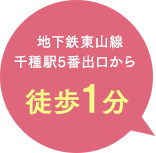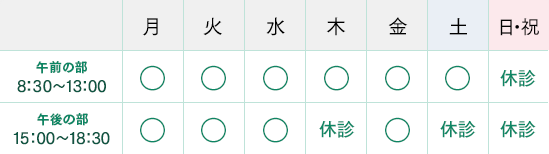香害について(その2)
Ⅳ 香害は好みの問題ではなく、製品による被害
「香害」で特に問題となるのは、ニオイに対する個々人の感性が異なるため、周囲の理解を得ることが難しいことです。特定の製品のニオイで体調不良を起こしたと訴えても、香りは「好みの問題」、「感覚の違い」、「遺伝子の問題」、「過敏な人だから」などの理由で相手にされないことが多くあります。「香り」や「におい」という言葉は、「甘い香り」、「良いにおい」「香りによる癒し」など、高感度のイメージで使われることが多く、アロマの精油がもつ身体への効果は昔からよく知られています。ところが、2000年頃から我が国では、メーカーが競って合成洗剤や柔軟剤などの生活用品に、人工的な香りを添加した新しい商品を売り始めました。「香り」が商品の新しい付加価値となったのです。そして、2009年アメリカから強い香りの柔軟剤「ダウニー」が輸入され始めてから、人工的なニオイで体調不良を訴える人が続出し始めました。
Ⅴ マイクロカプセル香害
「香害」による健康被害をさらに深刻化させているのが、柔軟剤などに含まれるプラスチック製のマイクロカプセルです。メーカーは「はじける香り」「香りが長持ち」「ナノ消臭成分」など、次々と新しい機能を付与した製品を発売しています。プラスチック製のマイクロカプセルの中に香りや消臭成分を閉じ込める技術が開発されて、香りが長持ちするようになりました。柔軟剤の一つのパッケージの中には何万個ものマイクロカプセルが入っています。マイクロカプセルの素材は、ウレタン樹脂やメラミン樹脂ですが、最近ではデンプン由来の物質も出始めました。
環境中にこのような微小プラスチック片や、マイクロカプセル素材の合成樹脂モノマー(単分子)が飛び散り、それに加えて消臭成分や香料など数多くの人工化学物質を吸入することで、香害が起きていることが推定されます。
Ⅵ 「香害」の特異性
1)家庭用品が原因:被害の発生源が消費者の生活空間にあり、香り付き合成洗剤や柔軟剤などの家庭用品が原因。
2)性特異性被害:被害者の約8割が女性。家事に女性が多く関わっている現状が起因している可能性もあるが、女性が人工的な香りにより反応しやすいことも考えられる。
3)「嗅覚過敏」と「嗅覚疲労」:嗅覚には順応や疲労という特徴があり、同じニオイを嗅ぎ続けるとニオイに麻痺して「嗅覚疲労」に陥ります。嗅覚過敏の人と嗅覚疲労の人の二極化が起こります。
4)人工物を天然と誤認:家庭用品に添加されている香料の90%以上が人工的に合成された香料です。天然のイメージに騙されて、人工化学物質を吸い込んでいるのです。
Ⅶ 「香害」は石油文明を象徴する公害
2019年ヨーロッパ化学品庁はマイクロビーズだけでなくマイクロカプセルの使用中止を提言しました。これらは環境汚染を進めるだけでなく、人体も汚染するからです。香害は現代の石油文明により作られた数多くの人工化学物質がもたらした21世紀型の空気の公害です。
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月