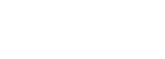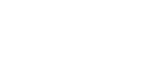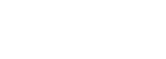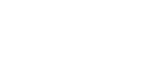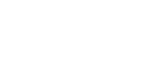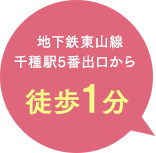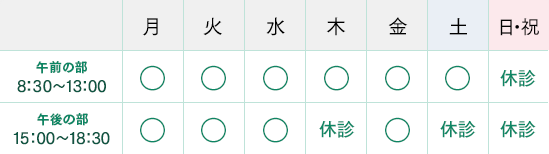女性の肥満・肥満症(その2)
Ⅲ 妊娠中の肥満と妊娠合併症
妊娠・分娩の回数と共に一部の女性で肥満の程度も増加することが知られています。特に、妊娠20週までに体重の増加が多ければ、妊娠中の体重増加が過大となり、分娩後にも肥満になりやすいことが指摘されています。
「肥満妊婦」では妊娠中の合併症や分娩異常が増加することや、妊娠高血圧症群や、妊娠糖尿病の合併頻度は肥満度と共に上昇します。肥満者を妊娠前に減量させることは新生児の予後を改善すると考えられています。
Ⅳ 閉経後の肥満と健康
1 閉経後の内臓脂肪蓄積
肥満者の割合は、男性では40歳代をピークに年齢と共に減少するのに対して、女性では40才から肥満者が急増し、年齢と共に増加し続けることから、閉経後に特に肥満が増加すると考えられています。全身的な体重増加そのものは加齢に伴う変化で、エストロゲンの欠乏とは関係ないと考えられています。しかし、閉経後に内臓脂肪型肥満が生じることは明らかで、これは脂質異常症、高血圧症、糖尿病などの重要な危険因子であり、閉経後女性に急増する心血管疾患の原因としても重要です。
2 なぜ閉経後には内臓脂肪が蓄積するのか
脂肪細胞から分泌されるコルチゾールを活性化する物質(HSD-1)が閉経後の女性で増加するため、閉経後の女性で内臓脂肪蓄積が亢進すると考えられています。
3 閉経後の肥満と疾患
閉経前後の女性にみられるホットフラッシュは更年期症状の1つですが、肥満女性は非肥満女性に比べてこの頻度が高く、症状も強いことが知られています。このホットフラッシュが減量により改善することが知られています。
これまで、やせは大腿骨近位部骨折の危険因子とされ、肥満女性では、荷重による骨密度の増加や脂肪組織からのエストロゲン産生の可能性から、骨折を起こしにくいとされてきましたが、肥満女性が非肥満女性に比べて、足首と大腿の骨折が増加することから,決して肥満が骨折を減らさないことが明らかになりました。
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月